
りんご評価用語集をつくりたい

りんごの美味しさを具体的に言語化した「りんご評価用語集」を作りたい。
美味しさ(味、香り、食感)を、甘い、酸っぱい、シャキシャキくらいでしか表現できず、もどかしさを感じています。
9月から、本サイトでコラムを執筆させていただいており、多種多様な品種の味や風味、食感をレビューするソムリエじみたことを書いていますが、りんごの美味しさを上手に表現できずに悩んでいます。
「黄王」を食べたときも、「つがる」を食べたときも、両方で酸味を感じたが、酸味の種類が違う。だけど、どう違うのかをうまく言葉にできませんでした。
味覚を言語化するのに、何か参考にできるものはないか。
探した結果、スペシャルティコーヒーの評価用語集にたどり着きました。
上質なコーヒーのテイスティングの評価基準に使われていて、例えば、鮮やかな酸味、ソフトな酸味、鋭い酸味、薄い酸味など、どういう酸味なのかをより正しく表現し、評価できるようになっています。
この用語集のりんごバージョンがあったらいいなぁー。
ネットで探してもない。
じゃあ、作るしかないかーと思ったわけです。
今年度中の完成を目指して、動き出したいと思っています。

作れなかったときの言い訳も書いておきます。
そもそも味覚はやはり言語化しがたく、生理上の裏付けがあります。
「においという感覚がとらえにくいのは、脳の構造と関係があると私は思っています。嗅球から伸びた神経は、二つに分かれて、一方は大脳の新皮質に入るのですが、もう一方は辺縁系に入る。つまり嗅覚の情報の半分は、いわゆる「古い脳」の方へ行ってしまい、言語機能をもつ新皮質には届かないんです。視覚の場合は、情報がすべて新皮質に入りますから、目で見たものは言葉で表現しやすいのですが、半分しか届かない嗅覚ではそうはいかない。」
引用:日経サイエンス(編)『養老孟司 ガクモンの壁』
続けて、味覚も情報が半分しか新皮質に入らないと指摘していました。つまり、美味しさを分析的に言語化するのは難しいというわけです。
できなかったとしても「脳」のせいだと言い訳するつもりなので、ボチボチがんばってみたいと思います。
【穗坂修基(ほさかもとき)】
弘前市相馬地区の地域おこし協力隊。
生まれも育ちも横浜市。Iターン者。
 りんご大学はりんごに関する色々なことを楽しく学ぶことができるバーチャル大学です。
⇒ りんご大学ホームページはこちらです。
りんご大学はりんごに関する色々なことを楽しく学ぶことができるバーチャル大学です。
⇒ りんご大学ホームページはこちらです。
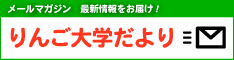 「りんご大学だより」は、りんごの魅力やりんごの最新情報などを週1回お届けするメールマガジンです。ご登録は無料です。あなたもりんごのある美味しい生活をはじめてみませんか? ⇒ 配信ご希望の方は、こちらへ
「りんご大学だより」は、りんごの魅力やりんごの最新情報などを週1回お届けするメールマガジンです。ご登録は無料です。あなたもりんごのある美味しい生活をはじめてみませんか? ⇒ 配信ご希望の方は、こちらへ
